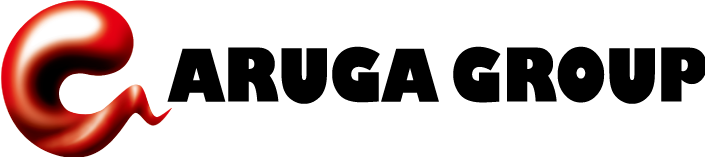4日目 経営方針共有勉強会
今月のテーマ
《小笠原流 礼儀作法 》

・・・・・・・・・・・・・・・2016年12月1日
・・・・・・・・・・・・・・・有賀泰治
700年の伝統を誇る小笠原流礼法の女性宗家、小笠原継承斎氏の書物より抜粋
1、礼法
足利三代将軍義満の命によって、今川氏、伊勢氏、小笠原氏が武士の一般教養を目指した『三議一統』の編纂が行われ、のちに小笠原流といえば礼法という基盤を作ったと考えられている。
(1)『三議一統」には「仁」と「義」についての「情けと道理の教え」がある。
周囲に対する思いやりのこころを大切にしながら、己よりもまず他者を重んじることを先とし、慎みの気持ちを忘れることなく周囲との和を育み、ものごとのに対する善意を見極めて潔く生きる武士のとしての心意気を説いている。
他者を守るほどの強さがある人は、他者へのやさしい気持ちを兼ね備えている。そのやさしさは、作法のあらゆる箇所に表現されている。
時代が変わり、あらゆる環境や機器が発達しようとも、どんなに便利な時代に生きようとも、人はたった一人の力では生活していくことは困難です。周囲の人とよいコミュニケーションを育む努力を怠ってはならないのではないだろうか。だからこそ、こころを鍛え、一つでも多くの作法を身につけて、状況に応じた、臨機応変で、やさしく、優美な振る舞いを心がけていくことです。
(2)「義俠」(ぎきょう)
義俠とは、正義のために強者を抑え弱者を助ける勇気を指す。男伊達とは、義俠のことであるほかに、「任侠」(にんきょう)という言葉は、強者をくじき弱者を助ける気性が強いことを指し、「仁義」というのは任侠と義俠からできた言葉。
「仁」は「人」と「ニ」から成り、重い荷物を背を丸くした人の意で、また、「ニ」は悲しみの意も表すことから「しのぶ」「したしむ」「いつくしむ」「おもいやり」「なさけ」などの意味がある。「義」は「羊」と「我」から成り、舞の美しい姿、礼を行う美しい姿の意味で、「礼にかなった美しい立ち振る舞い」、「道理」「ただしい」「譲る」「よい」などの意味がある。
2、姿勢
礼儀作法は知識を得ただけでは十分といえない。あらゆる状況に遭遇することによって、身につけた知識や振る舞いを磨きをかけ、日々研鑽を積むことが大切。
相手に対する心遣いを「作法」という形式にあてはめて表し、失敗や危険が伴わないように行動すること、また、美しく流れるような動作で行動することを大切にする。
当時の武士は、差している刀の長さ、兜や鎧の大きさも含めた、「自分が占める身体の幅」を意識して動いていた。
人間関係のなかであらゆる予測をし、それに適った作法で振る舞うことが大事で、その振る舞いにはすべて理由が存在する。
(1)正座
小笠原流では、正しく整った姿勢を「生気体」(せいきたい)、整っていない悪い姿勢を「死気体」(しきたい)と呼ぶ。
伝書には「尻とかかとの間に紙が一枚あるような気持ちで座る」と説かれている。つまり、上体の重心は腿の中間あたりに落ち着くようなイメージ。
1)正座のポイント
① 髪の毛を後ろから引っ張られているようになイメージで上体を伸ばし、下腹部に力を入れ、背骨を腰に突き刺す感じで背筋を伸ばし、腰を据える。そして力を抜く。
② 膝下は、男性は握りこぶし一つ分程度開ける。女性は合わせる。
③ 足の親指は、3〜4cm程度重ね合わせるように。
④ 手元は、指先を揃えて軽く丸みをもたせ、改まっているときは手を重ねず、腿の上に自分から見てハの字なるように置く。
⑤顎は引く。
⑥呼吸は腹式呼吸を心がける。
⑦和室においては正面に目線を置かず、一メートルほど先を見るようにする。
(2)立ち姿
自然な「胴づくり」を心がける。
「胴はただ常に立ちたる姿にて退かず掛からず反らず屈まず」
とある。退かずとは右に、掛からずとは左に、反らずとは後ろに、屈まずとは前に傾かないということ。正しい姿勢は、身体が前後左右に傾くことなく、無理のない自然な上体を示す。これを「胴づくり」とよぶ。
1)立ち姿のポイント
①上体の伸ばし方は、正座と同様。
②重心は、頭の重さが土踏まずに落ちるようなイメージで。
③足元は、立っているとき、また椅子に座っているときも、左右のかかとをぴったり合わせ、つま先は開く。女性は合わせせる。
④両手は指先を揃えて軽く丸みをもたせ、体の脇に自然に下ろす。
⑤頭は前に出ない。
⑥正座と同様に下腹部に少々力を入れるが、背、肩、首には余分な力が入らないように。
正しい姿勢は、精神面につながったている。何かに集中しようとする際には、心を集中させるという思いの表れがでます。それが姿勢に現れます。
さりげない立ち姿は、全ての動作の基本となり、無駄のない洗礼された姿は、己の心のあり方そのものです。
(3)お辞儀と礼三息・・・慎み深く、堂々と
お辞儀は非言語的コミュニケーションの最たるものである。ことばを用いなくても、相手に対する感謝や敬意を表すことができる。
お辞儀は相手への心の表れであり、それは一方通行でなく、両者が心を込めて行うことで、互いの気持ちの交流が可能になる。
1)立礼
立礼には、「会釈」「浅めの敬礼」「深めの敬礼」に分けることができる。
① 会釈
両脇の手が股の前に来る程度まで、上体を倒す。15度程度
会釈はお辞儀でありながら慎みの姿勢として用いられ、目上、高位な方をお迎えする際にも適している。
また、部屋の入退室、お茶を運ぶ、あるいは道や廊下で人と行き交うさいなどに用いられる。
② 浅めの敬礼
両脇の手が、会釈よりも少々、膝頭に近づく程度まで、上体を倒す。30度程度。
相手と対面する。あるいはお暇する際に用いる。日常的なお辞儀である。
③ 深めの敬礼
両脇の手が膝頭に届く程度を限界として上体を倒す。45度程度。
感謝やお詫びを伝える時に用いる。
④ 礼三息
お辞儀で身体を倒してから、元の姿勢に戻るところまで、ゆっくりした動作を行う。息づかいをする。
ア 息を吸いながら上体を倒す。
イ動きが止まったところで息を吐く。
ウ再び息を吸いながら上体を起こす。
2)座礼
①指建礼(しけんれい)
正しく座った姿勢から、腿の上にある両手の指先が畳につくまで身体を倒す。
座布団に座ったままお茶などが運ばれてきた方へのお礼を伝える。
②折手礼(せっしゅれい)
身体を傾け、手のひらが畳についた上体で、指先が膝頭と一直線に並ぶ。
挨拶の向上を述べる際や、床の間掛け軸や花などを拝見する際にもちいる。
③双手礼(そうしゅれい)
立礼の敬礼にあたる。時、場所、状況に応じて深さが異なる。両手の手首が膝頭に並ぶあたりを起点とし、両手の指先がつく手前までを限界とする。通常は左右の手の間に握り拳一つ分程度開いたところで止める。
知人宅を訪れた際、部屋に通されてから最初に交わす挨拶やおいとますときもちいる。
(4)歩き方
小笠原流の歩き方は、「ねる」「はこぶ」「あゆむ」「すすむ」「はしる」など、速度から息づかいまでが時、場所、状況に応じて使い分けられていた。
両足を平行にして一本の線をはさむように歩く、と心得る。まず、少々前傾の姿勢で、足裏が平行に進むような意識を持つこと。前へ足を運ぶ際には、踏み出した足には力を入れず、残っている足に体重をもたせておき、さらに踏み出した足へ重心を徐々に移していくよう、つねに身体の重心が中心にあるような体重移動を心がける。後ろの足はひきずるのではなく、身体についてくるような意識での体重移動が大切である。足先でなく股で歩くようなイメージをもつと、身体の揺らぎや膝を大きく曲げるのを防ぐことができる。
正しい姿勢で歩くこと、心も正される。
(5)「礼三度に過ぐべからず」 ・・・ゆとりある振る舞いでこころを伝える。
丁寧な挨拶というものは三度ほどが好ましい。相手のお宅に伺ったさい、玄関、部屋、暇の三度ほどが好ましい。また、1回の挨拶で行うお辞儀は少ない方がよい。その方がゆとりをもって心を込めてお辞儀がしやすくなる。
ことばを用いることなく、相手に心を伝えることのできるお辞儀の素晴らしさがある。
3、席
(1)次席 ・・・高座をこころがけるは田舎人のわざ
「高座を心掛るは田舎人のわざなり」 という伝書の一節が示すように、昔から高い座に座りたいという思う気持ちは、卑しいものとされてきた。
しかもこの箇所の前文には「我があるべき座より下りて居るべしと思う心持肝要也」とある。自分の座るべき位置にある席よりも下座の席にすわること、すなわち慎みの心を持つことが大事である。
相手の立場や相手の関係などにより、配慮などが必要だが、どの席に座っていただくか招かれる側にとって心地のよいか、ということを考えならが席を設けたいものである。まt、招かられる側となった場合には、もてなす側の心遣いを受け止められるだけのゆとりを持って、それぞれの席に伺いたいものです。
存在感ある人は、どの席に座っているかにかかわらず、自然と周囲にオーラを放っていることを忘れないことです。
(2)慎みのある行動 ・・・感情をすぐかたちに表すことを避ける。
自分の感情をすぐにかたちに表すことはできるだけ避けたい。
「御前に伺候のとき・・・扇を使うべからず。汗をぬぐい鼻をかむべからず」
と、暑いからといって、人がいる前で扇子を取り出して使うことは、慎みにかけた自分勝手な立ち振る舞いであると考えられていた。
慎み気持ちを行動に取り入れていた小笠原流には、軽いものを重々しく大切に扱い、また、重いものを持つ時には、顔をしかめていかにも重いものを持っているかのように振る舞うことは見苦しいとので慎むようにと教えがある。押し付けがましい立ち振る舞いをできる限りさけ、さりげない心遣いから発した慎みのかたちといえよう。
自分の気持ちをおもむくままに振る舞うことは慎むべき、という判断とそれに基づく振る舞いが肝心。
暑いとき、寒いとき、疲れているとき、悲しいとき・・・どのようなときも常に周囲への配慮を忘れずに振る舞うのは難しい。ーだが、その難しさを克服した先には、磨かれた人が持ち得ることのできる、優美な振る舞いが存在する。
(3)礼の省略 ・・・自分の存在を目立たせないという礼儀
「惣別 貴人 主人の御前にては さのみ万事に礼を深くするごと慮外の儀なり」
さまざまな場面において活用するべき大切な心構えである。全てのことに礼を深くすることはあってはならず、自分の置かれている立場や状況をしっかりと見極め、その場にふさわしい振る舞いをすることを忘れてはならない。
「貴人に対して礼儀するは貴人に対して非礼なり」
とも説かれている。一見すると、上の立場の方に礼儀を省くことが非礼であつ、と思ってしまいがちだが、ときには相手を敬うゆえに自分の存在を目立たなくすることも必要、という意味。空気のように存在することが、最も礼に通ずる、ということもある。
(4)残心・・・ しめくくりに数秒、心を込める。
「残心」とは相手に対する心を最後まで残す。たとえば、お辞儀を行う際には、必ず残心を取り入れる。お辞儀に礼三息を取り入れ、さらに上体が元の位置に戻ったあと数秒、こころを残すこと、すなわち間を取ることで、お辞儀に深みが生まれる。
つまり残心は、心のゆとりそのものを表すのである。すぐに次の行動に移りたいという気持ちが勝ってしまうと、お辞儀の印象が軽くなる。
「人を送り申す次第は賞翫(しょうがん)の方をば次の座にて一送り 縁にて一送り 庭にて一送り是第一也。猶も敬い候得ば門外までも出られ候。其次御座敷にて一送り 縁にて一送り 是第二也。又次の座敷まで出候て一送り是第三也。」というように、お客様を送る際、特に敬う人に対しては門まで行き、見送ったのである。
最後まで相手に対するこころを残し、互いのこころを通わせることが大切である。
電話を切る際にも残心は欠かすことができない。互いに終わりの挨拶が終わるや否や、電話を切ることは失礼である。忙しいなかにあっても、互いが挨拶を終えたあと、数秒おいてから受話器を置くくらいのゆとりは欲しい。
「残心」は「間」である。残心を大切にする人は、雄麗なこころを持っているに違いない。
4、食作法
食の美味しさは食材や料理方法だけに左右されるものでなく、誰と一緒に食べるかが重要な要素である。だからこそ相手の人からは、一緒に食事をして楽しいと思われる人は、室町時代かにおいての食事作法も、こうした考え方が根底にあって成り立っていた。
「人前にて飯喰い候様さまざま申し候えども前々申し候ごとく貴人を見合わせて喰うべし」
食事に関してさまざまな作法が存在するが、相手の食べるスピードや相手の気持ちに合わせて食事を進めることが大切だということである。
相手の気持ちに合わせながら食事をするには、作法にとまどうことなく、心にゆとりを持つことが前提でありそのために心得ておくべき食べ方や立ち振る舞いがある。
(1)和食の作法 ・・・「箸先五分、長くて一寸」
一寸は約3.03cm。箸先の汚れは少ないほど良い。同席の相手に不快な印象を与えずにすむためにも大切な心得。
正しい箸使いは、感謝の気持ちを表すに繋がる。食事にはたくさんの人々やその食材の命、たくさんのパワーが存在している。それを頂戴する、ということに対する感謝の気持ちを表しながら食を進めるのは、いつの時代も同じ。
正しい箸の持ち方
まず、箸先から三分の二あたりを持つこと。上の箸は、人差し指と中指ではさみ、親指で支える。下の箸は、親指と人差し指の付け根にはさみ、薬指で支えて固定する。
小笠原流では箸の先の汚れで、その人の嗜みを知るというほどの話があったようです。
楊枝の使い方
「楊枝を使うこと・・(略)・・口にてをかざすごとくにして、わきへ向きてつかいm鼻紙を取り出して口を拭き、使いたる楊枝をも懐に入るるなり」
「食事の仕方で相手の人柄を垣間見る」と言われることがある。毎日行う食事、その立ち振る舞いを通じて、その人の心のあり方が分かってしまうのは当然なこと。
(2)酒の作法 ・・・席を楽しくする心遣い
1)「若き者などは乱舞の座にのぞみて口をつむぎたるは見苦しきものなり」
人が集まる酒の席において、若者は、所望されたらい一通り舞ってみるほうがよいのであって、こうした場において壁の花になるのは見苦しい、ということである。
このような心得は、一見すると、「目立たないということ」との整合性に欠けるようにも思えるのだが、決してそうではない。酒の席における、場の雰囲気を楽しくしたいと思う気持ちから成る振る舞いの根底には、常に自分の立場をわきまえ、自分だけを売り込むような行動に通じることがないようにという心がけがある。それがなければ、この心得が成立しないのである。
現代の酒の席においても、心得のある人は、いつまでも周囲の目が自分だけに向くようにするのではなく、場が盛り上がって全体が楽しい雰囲気になったところで、自然に自分の存在を消すことのできる配慮があることと同様である。
「いささかも油断なくきをつかうべし。こと酒杯に酔い候えばこころがけてさえ落度あるものにて候」・・・当時も酒の席での失敗は多かったことがわかる。
2)盃の酒を飲むさいの心得
「一つゆとは酒をすきよみて下を捨てるに一露落ちたるを申し候」
「一文字と申し候はこれも下にて一文字を引き候に下多く候えばならず候。また下候わねば一文字引かれず候。この二つの呑みよう大事にて候」
「女の盃に口をつけて呑むべからず」
「一味同心」の団結が酒の席で高められ、同じ盃を酌み交わすことで、お互いの信頼の証を認め合ったのであろう。
気が緩みがちな酒の席においてこそ、周囲の気遣いを忘れないようにする人に対しての信頼度は高まるものである。
3)酌の心得 ・・・酒を飲めない人への気遣い、女性への気遣い
小笠原流には、酒を受ける作法のみならず、お酌をするうえでの心得も多く残されている。
「下戸は盃をとりざまに御酌の顔を見るべし。是は下戸というしるしなり。酌 心得べし」
「酌心なくして入れたならば力なくすきと呑むべし」
「二度は心得をして三度つぐとは二度つぐまねをして三度目をつげようとなり。しかれば酒少しなり」
儀式のさい酒はつきものだったが、いつの時代にも、上戸、下戸ともに存在しているわけである。だからこそ、そうした人への心遣いも必要であり、祝いの儀式のさいには、二度つぐ真似をし、三度目をつげようのみ酒を注ぐことで下戸の人の負担を軽くするようにとの心得も存在した。
酌に関しても目立たない心遣いができる人は、あらゆることに機転のきく人ではないだろうか。
4)宴席 ・・・知り合いの人以外とも会話をする。
パーティーや結婚披露宴などにおいて席についた後、出席者が忘れてならないのは、同じテーブルの人との会話を積極的に行うようにと努めることではないだろうか。周囲の人のことを考えると、互いに挨拶を交わし、会話を弾ませるように心がけることは出席者としては当然な姿。
「御主の御機嫌も知らず物を披露するは然るべからず。よく次宜を伺い候て何事も申すべき事なり」
相手の気持ちの状態をわからないまま、話しかけることは控えるべきであり、時、場所、状況を考えてから伝えようとする心配りが大切である。
プライベートのことや相手が好まないであろう話題を控えるなど、相手の気持ちや状況を見極めてから話しかける気遣いを忘れてはならない。
5、ことば遣い
(1)言霊
ことばには不思議な力が存在するとして、ことばそのものを大切に考えて発していた。ことばを大切にする精神を失ってはいけない。
本来、ことば遣いは家庭で躾けられるものだが、親となる世代の人でも、ことば遣いの心得がないようになってきた。子供が乱暴なことばを用いても仕方がない。
社会人になってもラフな言葉遣いで会話を進めている人がすくなくない。しかし、美しいことば遣いは日本文化の大切な財産の一つと捉えて、身に付けるべきではないだろうか。
美しいことば遣いとは、敬語を身につけることのみを指すのではない。声の大きさ、ことばを発する間、速度、イントネーション、顔の表情・・・ことば遣いに付随する多くの心得を身につけ、実践して、初めて相手の耳にそれぞれのことばが一つの美しい流れとなって届くのである。
次に「間」を大切にできない人は、ことば遣いの配慮に欠けている人である。好ましいコミュニケーションには、一方通行で話が進むもではなく「話すこと」と「聞くこと」のバランスが必要だ。
人前にもかかわらず、他の人話にことばをはさんだり、目上の人のミスを表だって指摘する。人前で目上、上司を諫言(かんげん)することは、社会人として無責任な対応に過ぎない。
(2)敬語の使い方
敬語には相手を敬った表現をする「尊敬語」と、自分自身がへりくだった表現をすることで相手を敬うことにつながる「謙譲語」があるが、さらに「お」や「ご」をつけたり、文末を「です」「ます」とすることで丁寧な印象をつくる「丁寧語」がある。敬語で大切なことは、丁寧さを心がけながらも過剰表現にならないこと、また尊敬語と謙譲語を正しく用いることである。二重三重敬語はかえって耳障りであるし、へりくだった表現である謙譲語を相手の表現に使うことほど、相手に対して失礼なことはない。
敬語は先人たちが生み出した、人間関係を円滑にするための知恵である。
(3)手紙
初めてお目にかかった方、お世話になった方、門弟など宛先はさまざまであるが、手紙で常に心を込め筆先に伝え、受け取った多くの方は喜んでいただけることでしょう。文字によるコミュニケーションの素晴らしさを痛感する。
昨今は文字を使用してのコミュニケーションツールは、Eメールだろう。だがEメールは、便利だからこそ、一方的で略式的なコミュニケーションツールであり、人に依頼をする場合やお礼を伝える場合、手紙に勝るものはない。
手紙の構成(封書)
《前文》
①頭語
②あいさつ文(時候の挨拶、相手の繁栄、活躍、健康などを喜ぶ挨拶)
③お世話になっていることへの感謝
(主文》
④ 転語、起辞(「さて」など、接続詞や接続語を用いて前文と主文をつなぐ)
⑤ 用件
《末文》
⑥結びの挨拶
⑦結語
《あとづけ》
⑧発信日
⑨差出人名
⑩宛先
11わきづけ
《追って書き・副文》
書き残したことや追記したいことを「追伸」などに続けて書く。目上の方や改まった場合には用いない。
「脇付」 とは直接相手に手紙を渡すことを遠慮し、相手の住まいに仕えている人宛に送る、という控えめな気持ちを表す。宛先の左下に小さめの文字で書く。
「机下」(きか) とは、相手の机の下へこの手紙を慎んで差し上げます。という意味である。
脇付にはそのほかにも、「御侍史」(おんじし)「足下」(そっか)など多数あり、女性に対しては「御前に」「御許に」(ももとに」などを使用する。脇付を用いるさいは、便箋の宛名、封筒の宛名、どちらにも書くこと。
はがき
はがきは誰からも内容が読まれてしまう可能性があるので、略式なものである。したがって、目上の人に差し上げるのは相応しくない。使用したいはがきがある場合は、そのはがきを封書に入れることをおすすめする。
手紙は字の上手い下手ではない。書き手が相手への思いやりを忘れることなく、思いを込めて丁寧に書くことによって、相手に対する気持ちは通じるはずである。そのためには、手紙を書くタイミングを逃してはならない。
こころに届く手紙をしたためられる人は、手紙に鮮度があることを知っている。
(4)毎日の挨拶のことばを丁寧に
目覚めてから家族と対面するさいの「おはようございます」にも共通するが、相手のあいさつがすがすがしい印象だと、こちらの気分もよいものだ。ならば、相手の丁寧な挨拶を待つのではなく、自ら活気ある挨拶をするべきではないだろうか。
6、つき合い
(1)諫臣(かんしん)を持つ人、持たない人・・・(主君に諫言(かんげん)する家臣。「人君にして―がなければ正を失い」〈中島敦・弟子〉
上司と部下であれば、自分に都合のよいことばかりいう部下ではなく、時には少々の辛口のこともいってくれる部下を大切にすることこそ、人の上に立つ者として相応しいこころがけであった。
それは現代においても同様であり、上司のご機嫌を伺っている部下ばかり周囲に配置するこよや、上司に問題提起をできない空気をつくってしまうことは大きな問題を招く危険性がある。
ただし、諫言する側は、状況を判断した上で自分の考えや思いを伝える方法を配慮することを忘れてはならない。
そして、どんな立場になろうとも、相手の話を真摯に聞きき、自然と周囲から信頼を寄せられる人として成長しなければならない。
「仁はみずからをわすれ他をはぐくみ危きを救う」
自分の考えを貫き通そうとするのでなく、相手を尊重したうえで問題をかいけつするためには、こころを傾けて話を聞き、現状を把握しなければ対応できるわけがない。それこそ人に対する思いやりともいえよう。
(2)察し合うこころ
「故人も礼の用 和を貴むとやか仰せられし由」
礼の作法というのは和を重んじることである。「和」とは調和のことで、相手や環境を考えながら、臨機応変に対応することが大切なのである。
自分の立場や相手との関係を考え、自己を抑制し、相手のこころを察しながら、周囲の状況を判断することが必要である。
相手を褒めたり、長所に対して率直に目を傾ける。そのポイントとして “ 観察 ” という言葉がある。「観」は「みる、しめす」、「察」は「みる、しる、さっする」などの意味がある。つまり、相手のことを深くまで観て、思いを察することが「観察」なのだ。この「観察」なくして相手をはめることはできない。
「人の己を知らざるをうれえず 人を知らざるをうれえよ」
孔子の教えがある。自分のことを知らないことを心配するよりも、自分が人を知らないこと、つまり、認めていないことを心配するべきなのである。
「君子は和して同ぜず 小人は同じて和せず」
徳を持って人と交わり、上辺だけで相手を判断することなく、相手のこころを察し、和を貴ぶことのできる人になりたい。
(3)「先ず我が馬を道下へ打ち下ろして礼すべし」
これは、武士の間では、たとえ相手より自分の方が身分が高かったとしても、道を譲ってもらうことが当然だという考え方は存在していなかった。むしろ、上から下へ、下から上へと、お互いの社会的地位を認めたうえで、お互いを思いやるこころが存在し、さらにそのこころを行動に示し、互いの交流が無言のうちに行われていた。
(4)水は万円の器に随うこころなり
人の第一印象は、数秒、長くても15秒ほどで決定し、さらには、言葉によって決定される印象よりも、見た目から判断される印象の割合が高いといわれている。
目から入る要素として「身だしなみ」と「基本動作」、これに耳から入る要素として「ことば遣い」を加えた三つで人の印象は決定される。
身だしなみは二つの側面がある。一つは自己を満足させるための身だしなみ、もう一つは他人に不快感を与えないための身だしなみである。
「清潔感」、「こころの温かさ」、「相手への配慮」、昔からひとのこころの在りようが姿に映し出されるといわれてきたように、黙っていてもその人の姿から、感じとることができます。その見極める力をすべての人が持ちえているものでしょう。
あなたもです!
ならば、清潔感のある身だしなみは当然として、動作、ことば遣い、は自分本位に走るのではなく、相手を慮る気持ちを忘れることなく、周囲に心地よい雰囲気を漂わせることができる。これが小笠原流の伝書の中でも特に大切な教えであります。
「水は万円の器に随うこころなり」
水が器の形にかかわらず自然に存在することを例に、自己を主張せず、すべてに順応するように振舞いながら、自分の本質を失わないこころを持つ。
7、格好
(1)「格」とは木がまっすぐに立つこと
「品格」に込められた意味。
「品」は、人の口を三つ合わせた形から成る。ゆえに多くの人が話す。あるいは口は器物かたどるから物を示し、ひいては「じんかく」をも意味する。
一方「格」は、木と各(たかい意 = 高)から成る。ゆえに木がまっすぐに立つことを示し、ひいては「地位、身分」「流儀、ものごとの仕方」「規則、法則」などの意味がある。
品格には、身だしなみを整え、まっすぐに立つことが欠かせない。ここでいう「身だしなみ」「まっすぐに立つ」とは、清潔感のある服装で、姿勢を整え立つことのみをいうのではない。自分本位でなく、清らかなこころで、さらに自分の理念に向かってまっすぐ、心持ちが高くあることを示す。
また状況に応じて、相手を問わず、誰にでもわかりやすい美しいことばで話す。もちろん、ことば遣いに関しても、相手を軽んじ、自分のばかりを引き立てようとする思いが存在しては、まっすぐに立つことはできないはずである。このようなことが少しでも実現できると、周囲から「品格がある」と言われる人に近ずくのではないだろうか。
さらに、相手の行動や発言から、品格がある、あるいは品格がない、という印象を持ってしまうことはある。
気品
品格と並んでもう一つは大切な事は、「気品。きひんは、気位の意味もある。品性を保とうとする気持ちが、気品であり、気位なのだ。
つまり、気品がなければ、品格も存在しない。品格のある人は日々の行動に対し、誇りを持っている人をいうのではないかと思う。
その誇りは公私にかかわらず、自分は周囲から後ろ指を指されるような偽りがあったり、自己中心的な生き方をしていないということに対する誇りである。
そう考えると、品格は生まれながらに備えているとは限らない。心がけのいかんによっては、増やすこと、減らすこと、どちらも可能なのである。だからこそ、自己中心的な発想や立ち振る舞いは品格に欠けることを、肝に銘じておかなければならない。
志
さらに、品格は「志」ともいえよう。たとえ仕事で成功をおさめたとしても、それにおごっていては品格にが損なわれる。人生に向き合い、何をすべきかを常に自己に問いかけ、その志に向かって前進し続けることだ。
(2)覚悟と名誉
「武士道というのは死ぬことと見つけたり」
現代では極端な表現だとは思うが、武士は武士道を身につけるために、毎朝毎夕、命を捨てた思いで修行を重ね、奉公に尽くしたのであった。
日本において、鎌倉時代から発達した武士特有の道徳「武士道」は、江戸時代になると儒教の教えに結びついていく。奉公は、「お家」という運命共同体で生活していた武士たちが、「お家」の繁栄長久を願うゆえの生き方であったといえよう。また、封建制度の下で生きてきた武士にとって、上下の身分のわきまえ、その枠組みを命がけで守ることが、孫の代まで生き延びていく道だったのである。だからこそ、組織における自分の立場をわきまえながら、相手と一定の距離を保ち、人間関係を円滑にするために、礼儀作法が必要とされたのではないかと思う。
当時の武士は、使命感や理念、目標に向かって、決定的な瞬間には自分の身を案ずるのではなく、身を処する覚悟があったからこそ、「世」と「死」の二元相対するなかにおいて、「死」に動じることのない強い精神を持っていたのであろう。行動の覚悟は、こうした強いこころの覚悟が備わっていてこそ身につくことであり、その覚悟があるからこそ志を持つことができるのである。
名誉
さらに、追求するべきことと考えられたのは、自分の生き方に対する「名誉」である。多くの富を得ることでもなく、豊かな知識を得ることでもない、この名誉に対する思いには、潔さを感じる。
(3)身だしなみ
「人の衣装の色々すべて若き人もとしの程よりすこしくすみて出立たれ候がよく候よし申し伝え候。ひとの若くと出立ち候は似合わず候なり」
年配の人も若い人も落ち着いた様相を用いるのがよいとされていた。慎みのなかに美しさを求める装いは、着飾って自己を満足させるものではなく、むしろ相手の心にあわせて身だしなみを心がけていた。日本人の伝統的な心遣いを読み取ることができる。
「御小袖引合せの事。御襟にこころをとめ候はねばいかに美しき襟つきにても見苦しきものなり。御襟の合わせめ水ばしりにいとやわらかに御召候え」
という心得は、江戸時代、お姫様に向けて書かれた伝書の一説なのだが、男性にも通ずる教えであり、現代にも活かせられる。
襟の合わせ目は水が走るように自然であるようにという身だしなみの心得。ワイシャツの襟回り自分のサイズと合っているか、ネクタイが曲がっていないか、などに通じる。
日本には古来「ケの日」と「ハレの日」という考え方がある。ケとは、日常の仕事をする日のことであり、働くための着物を着ていることが習慣だった。
これに対して「ハレの日」は人生儀礼にあたる特別な日のことである。このような日には禊(みそぎ)をして心身を清めて、白衣を着ていた。このハレの日に着る白衣こそが、神事や行事の祭着や祝着、装着(よそおいぎ)といわれる晴れ着だった。現代では晴着と書くのが一般的。
「ただ男は若きも老いたるも白帷子(しろかたびら)似合い候」
派手な染物や金銀をあしらった豪華なものは、一人前の男性が着るものではない、と説いている。もっとも似合う帷子(夏の薄物)は白いものであり、それは質実剛健を重んじた社会の模範でもあった。
(4)目はこころの鏡・・・自分の表情をチェックする。
現代において、自分の印象をどのようにあらわすかが、周囲からの信頼度を増すための手段にもなります。
心にゆとりがなく、悩みごとがあるかと、自分では気づかぬうちに眉間にシワが入り、厳しい表情になっていることがあるかもしれない。だからこそ、鏡で自分の表情を日々確認するのは大切なことです。
身だしなみを整える点からも、鏡で表情をチェックして、鏡に親しんでいただきたい。
「目はこころの鏡」・・・孟子の教え。
周囲から信頼を持たれる表情、明るくやさしい表情を持つことは、周囲との円滑な人間関係をさらに深めることにつながるはずである。それには、まず、こころを磨くことも必要なのではないだろうか。年齢を問わず、素敵な表情を身につけたい。
(5)無心・・・自分の欲にかたよらず、こころを磨く。
日常生活の中で、すべての行動に相手への心遣いを持ち合わせるのは難しいことであるだろう。
礼法を身につける目的とは何か、ということだ。それは究極のところ、こころを練磨することともいえよう。
「無心」
人のこころが何かに囚われることなく無心になることは最も難しく、少しでも自分のこころを無心に近ずける努力をすることが大切である。自分の欲に偏ることなく、バランスのとれたこころを持つことが、こころを磨くことにも通じる。こころを鍛える努力はいつの時代であっても、この世に生を受けたからには忘れてはならないことではないだろうか。
礼法においては、相手が誰であっても、どのような立場の人であっても、相手に対する思いは控えめでなくてはならず、ゆえに相手によっては、自分が受けている、やさしい心遣いからなる自然で慎み深い振舞いに気づかない人もいるだろう。
だが、それでよい!
なぜなら、心遣いは見返りを期待しない気持ちから発していることが前提なのである。心が鍛錬され、作法に対する知識と行動が身につき始めると、状況に応じた適切な判断と、それに伴う自然な振舞いができるようになる。それには、ゆるぎのない強い信念が、こころに備わっていることが必要である。こうした信念や覚悟が備わった、内面に秘められた強い精神力が、人の優雅さや品格をつくりあげているのだと思う。
仕事に対しても、高い志と信念を持っていることが重要である。
雑念を払い、無の境地に達することは難しい。だが、命の灯火が消えるまで、こころを鍛錬する努力を怠ってはいけないと思う。