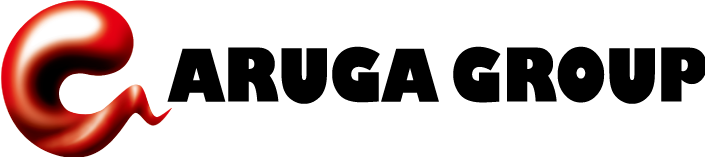経営方針共有勉強会
3ヶ月ぶりの勉強会
蜜を避け、少人数にして回数を増やして実施。
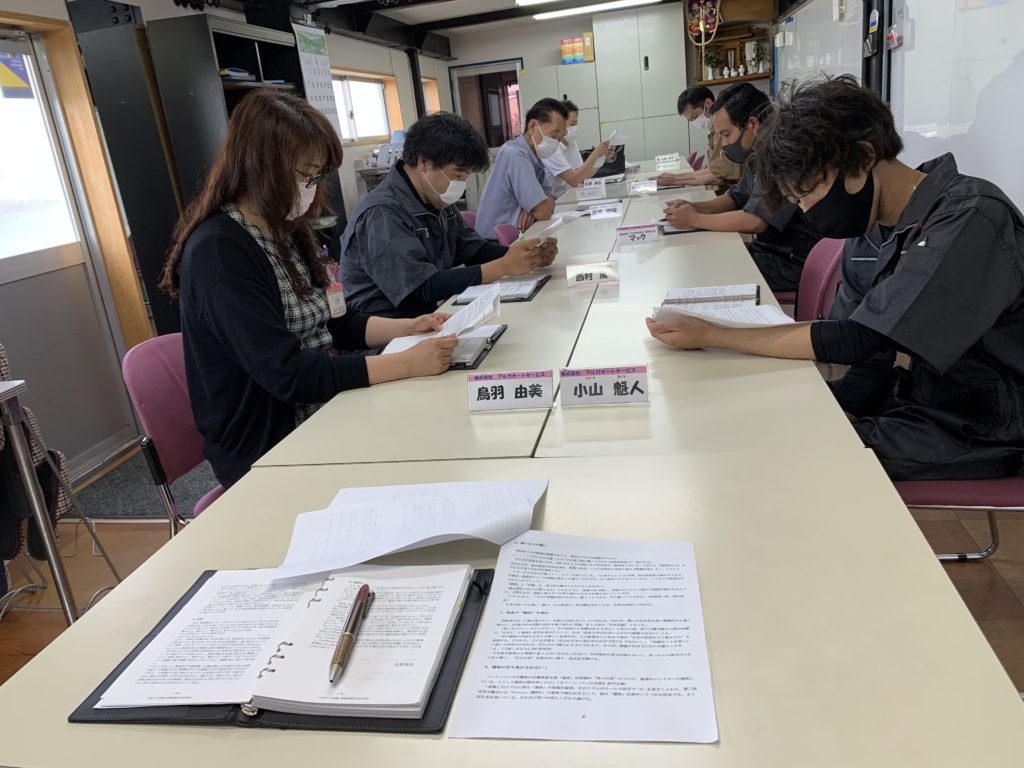
並柳店では4回実施 ↑

飯田店(橋本自動車工業) ↑
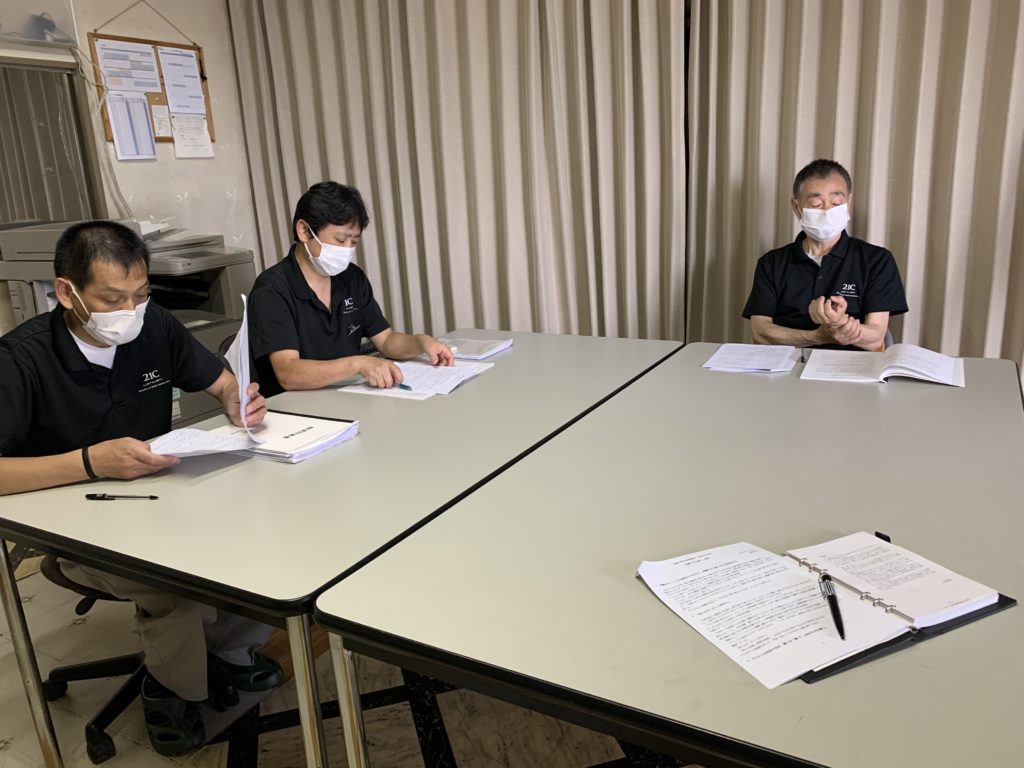
AAS ↑

あずみ野店 ↑
今月のテーマ 《 困難に打ち勝つ・執念 》
2020年7月1日
有賀泰治
1、困難がないことが幸福なのではない。困難に打ち勝つ中に幸福がある。
2018年の第76回名人戦七番勝負の第6局。佐藤天彦名人が羽生善治2冠に勝利を収め3連覇を達成した。
佐藤氏は2016年、史上4番目の若さ(28歳)で名人位に。その対局は「積み重ねの逆転術」と評される。派手さはないが不利な局面からも一手一手、にじり寄るように攻め続けて勝利をつかむ。氏は「形成が悪くなってからこそが本番だとさえ思います」と(『理想を現実にする力』朝日新書)
人生もまた、思わぬ難曲に遭遇することがある。その時にひるんで引くか、そこから粘り強く努力を重ねていけるかで、未来は大きく変わる。
会社や社会でも思わぬ事態や変化が訪れることが、しばしば起こる。そんなことに、最初は戸惑う子どもあろう、不慣れなこともやらなければならないこともあろう、懸命に取り組み打破する経験を積み重ねれば道は開ける。
どんな人にも困難は訪れる。それを粘り強く挑む人だけが、たくましく成長する。
2、「我々は月へ行くと決めた」
46億年続いた静寂(せいじゃく)の世界に人間が初めて降り立った。そのテレビ中継に7億ともいわれる人がくぎ付けになった。1969年7月20日のアポロ11号の月着陸から2020年で51年目になる。
アポロ計画で使われたコンピューターの計算能力は現在のスマートホンの1000分の1以下。しかしそこには、あらゆることを想定した英知が集結していた。その一つが“飛行士が間違えて操作した場合は再起動して回避する”というソフトウェアだった。
当初は「宇宙飛行士は完璧に訓練されているから、決して間違えない」という安全ソフト不要論がNASAで大勢を占めていた。だが実際、飛行士が用いたチェックリストに誤りがあり、着陸直前にこのソフトが作動。機器が操作不能になる事態を回避できた。(小野雅裕『宇宙には命があるか』SB新書)
無数のシュミレーションと訓練に裏打ちされた“絶対にミスしない”という自信は大前提。その上で、万が一ミスしても成功にたどりつかせてみせる。・・・そこまで考え、最後まで打てる手を打ち切る執念ありての“勝利”だった。
「我々は月へ行くと決めた」
「我々の技術と情熱を結集し、それがどれほど偉大であるかを証明するからだ」
とケネディ大統領は言った。宇宙へ向かって示された人類の誇りである。
3、どのような状況であれ、戦いは“勝つ”と決めた方が勝つ。
明治維新から2020年で152年。その維新回天の流れを開いたといわれる決起がある。1864年12月、高杉晋作が起こした功山寺挙兵(きょへい)である。
幕府になびく藩政府を打倒するため、彼は自ら創設した奇兵隊などに決起を呼び掛ける。だが、賛同するものは少なく、行動を共にしたのは80人ほどしかいなかった。しかし晋作は、徐々に味方を増やし、次々と奇襲攻撃を成功させ、新たな藩政府の樹立を導いた。
この挙兵は、晋作の「賭け」だったともいわれている。藩政府側の勢力は2,000人。80人の勢力で、勝てる見込みはない。それでも、彼には“自分が立ち上がれば、多くの同志が続く”との確信があった。事実、挙兵から3週間後には、奇兵隊が戦いをかいし。最終的に晋作の味方も2,000人までに増えた。
『勝ってみせる!』と決めて勝ち続けた。
4、本気
時は紀元前3世紀の中国。「戦国七雄(しちゆう)」に数えられていた斉(せい)の国に、田(でん)単(たん)という常勝将軍がいた。
田単が将軍に登用されたのは、斉が隣国の燕(えん)に大敗した時。首都を失い、二つの城を残すだけとなった国家存続の危機にあって、彼は智略を駆使し、自ら先頭に立って果敢に反撃。瞬く間に七十余城を奪還し、救国の英雄となった。
数年後、宰相(さいしょう)となった単田は、小国・狄(てき)との戦いに臨む。誰もが勝利を疑わなかったが、3カ月たっても攻め落とせない。悩んだ単田は賢者に教えを請う。賢者は答えた。かつての救国の戦いでは決死の覚悟があったが、今の将軍には、そうした「覚悟がおありになりません」。翌日気力を奮い立たせた単田は、敵に矢が届く場所に立ち、攻め太鼓を鳴らして全軍を鼓舞。ついに狄を破った。(林秀一著『戦国策(上)』明治書院)
「たぶん、大丈夫だろう」という甘さや慢心。「誰かがやるだろう」という人任せ・・・戦歴の勇者であっても、心の緩みがあれば、勝てる戦いも危うくなる。勝負の厳しさである。
『真剣な一人』『本気の一人』がいるところに前進がある。これが永遠の鉄則である。それと、活路を開くのは、ほかの誰でもなく、自分自身・・・だ。
5、殻を破る
セミの羽化。地中からはい出てきた幼虫が木に登り殻を破るまで約2時間。
羽化直後の羽は透けるように白く、うっすらと色づいたエマラルドグリーンが神秘的だ。「妖精みたい」に見える。だがこの美しい姿を世に現し、夏空へ羽ばたくまで、どれだけの戦いが必要だったか。羽化に適当な木が見つからないこともある。風にあおられ枝から落ちたり、天敵に襲われたりして半数が力尽きてしまうという。
成虫となったセミの泣き声を「この世界に生まれたうれしさと、自分がこうして生きていることの楽しさ表すために、歌っている」と表現したのは昆虫学者ファーブルである(奥本大三郎訳)。土の中で何年も過ごし、ついに殻を破った喜びの歌だと思うと、あの“騒がしさ”も心地よい。
人間にも「殻」がある。“自分はこんなものだ”と決め付け、卑下する心がその一つ。だが生命には“成長しよう”という本然のリズムが備わっている。
殻を破るとは決して“別の人間”になることではない。自身の可能性を信じ、秘められた力を発揮しようと挑戦を続けることだ。
焦らず、しかしたゆまずr。そこに人として生まれた本当の喜びもある。
6、弱い心との戦い
「勇気ある人の財産は破壊できても、勇気そのものは破壊できない」
・・・・・フランスの文豪・ユゴーの小説『海に働く人びと』(金柿宏典訳)の一節である。
ひときわ光彩を放つのが、1851年から19年続いた亡命生活だ。独裁者ナポレオン3世から「帰国許可令」が出されたが、彼は祖国の自由を求め、敢然(かんぜん)と拒否。この亡命時代に冒頭小説や『静観詩集』『レ・ミゼラブル』など多くの名作を発表した。
ユゴーの5代目の子孫マリー・ユゴーは述べている。「亡命中という19年間、彼は創造性の源の中で生き、芸術家・創造者としての時間を集中して過ごしたのです。もし彼がパリにずっといたら、ここまでの偉業はなせなかったでしょう」。
「創造」と「苦難」は、実は切り離せたものかもしれれない。
「鉄は炎打(きたい)で打てば剣(つるぎ)となる」とあるように、高温の炎で熱し、何度も打つことで鉄の不純物が除かれるように、人間もまた、試練と戦う中で自身に秘められた力を鍛え出していくのだ。
ユゴーいわく、「今日の問題は何であるか。戦うことである。打ち勝つことである」(神津道一訳、現代表記)
自身の弱い心と戦い、勝つ。その勇気の一歩を踏み出すことが、自身の成長につながる。
7、信念で“勝利”を進む
将棋界では「C級に落ちたら、B級には戻れない」といわれる。2019年、勢いのある若手多い激戦区のC級1組から、50歳の杉本昌隆八段がB級2組かに昇級。史上4位の“年長記録”となった。
「強くなりたい。あきらめない。その気持ちに年齢はありません」と杉本八段。弟子の藤井聡太七段の活躍に“自分も”と奮起し研究を重ねたという。氏は「成長や学びは若い人だけの特権ではない」とも。
一局の勝敗が昇級を左右する厳しい世界だが、その結果以上に杉本八段は“自分の状況をどう捉えるか”を重視する。すなわち、どんな苦境も「自分が不幸と思わなければ『負け』ではない」。「些細なことを楽しいと感じる気持ちがあれば、その人は『勝ち』を手に入れます。ならば、極論すれば『人生には勝ちしかない』」(『悔しがる力』PHP研究所)
不本意な結果から進路に迷う人がいるかもしれない。だが重ねた努力は消えないし、培った心の強さは人生の宝と輝く。“自分自身”を諦めない限り、道は必ず開ける。
8、運命に打ち負かされない!
ベートーベンの交響曲の交響曲第五番「運命」は冒頭の“四つの音”について、秘書のシントラーに説明している。こうして運命は扉を叩くのだ」(『ベートーベンの生涯』角川文庫)
一度聞くだけで心に残る「運命」の冒頭の旋律。そのリズムはモールス信号で「V」を表すことから、第二次世界大戦中には「Victory (勝利)」の意味で使われたという。彼は「運命」以前のいくつかの作品でも、よく似た音を用いている。それほど四つの音にこだわり続けた。
20代後半から耳が聞こえなくなるという絶望の中で、数々の名曲を生み出したベートーベン。自らの運命と格闘を続けた彼は語っている。「どんなことがあっても運命に打ち負かされきりになってはやらない。・・・おお、生命を千倍生きることはまったくすばらしい!」(片山敏彦訳)
運命は「命を運ぶ」と書く。わが人生のタクトを振るのは自分自身。過酷な運命にも、ひるまず立ち向かう時、人間としての底力が磨かれる。“断じて負けない”と決めれば、翻弄(ほんろう)された命が主体的になる。
苦難をバネに飛躍した人生は全て、人の心を動かす。“勝利の曲”となる。
9、未来を創るのは、私たちの一歩から
2019年、米国アカデミー賞で4部門を受賞した「ボヘミアン・ラブソディ」。英国のロックバンド「クイーン」を題材にしたこの映画の最大の山場は、チャリティーコンサート「ライブ・エイド」(1985年)での演奏シーンである。
同コンサートが行われる契機になったのは、英国のテレビがエチオピア飢饉(ききん)の惨状を、ある看護師の姿と共に伝えたことだ。この看護師はクレア・バーチンガー博士。長年、紛争地帯で医療活動に従事してきた。
博士が来日して語った話が印象的だった。戦闘が続くアフガニスタンでゲリラの司令官に尋ねられた。「あなたのような優しい女性が、こんな現場を変えられると思うのか?」。
博士は一つの格言を思い出し、こう答えたという。「水ほどに甘く、優しく、柔らかいものはない。でも、水には山を動かすだけの力がある」
水は人々の渇きを癒し、命を支える存在だが、それだけに止まらない。大きなうねりとなれば、大地を削り、山をも動かすほどの巨大なパワーをもつ。
民衆の力も水の流れに例えられるだろう。一人一人の行動は「小さな」ものかもしれない。だが、その積み重ねは「大河」となって社会を変えていく。
10、布石
白と黒の攻防を制したのは、11歳の日本人だった。(2018・11)
チェコで開かれた第42回世界オセロ選手権。36年ぶりに最小年優勝記録を更新した。
残り5手の時点で22対37。元世界王者のタイの選手が優勢に思えた。だが少年の次の一手で相手選手の表情が固まる。気付けば34対30。相手の打ち所を消した少年が逆転劇を演じた。
覚えるのに1分、極めるのに一生。そういわれるほどオセロは実に奥深い。「隅を取れば勝てる」と思いがちだが、そうとは限らない。いかに相手の置ける場所を減らし、置きたくない場所に置かせるか。勝負は最後の一手までわからない。
人生も勝敗は途中では決まらない。最後に勝つには何があっても返されない“誓いの布石”を打つこと。そして祈りを込めた“決意の一手”を放つことだ。そうすれば苦悩も喜びに変わる。人生はオセロ以上に奥深く、面白い。
11、誓願
群馬・高崎市の「上野三(こうずさん)碑(ひ)」は日本最古級の石碑として名高い。2017年、ユネスコ世界遺産に登録され、知った人も多いだろう。
三碑の一つ「金井沢碑」には、「誓願(せいがん)」の二字が刻みられている。奈良時代初期「三家(みやけ)」を名乗る氏族が仏教を信奉し、一族の繁栄を祈るために造立したものだ。当時の仏教の普及を知る上で重要な史料だという。
同じ「祈り」でも、いわゆる神頼みのような“おすがり”と「誓願」の祈りは異なる。おすがりとは、ひたすら神仏など他者の行動に頼ること。一方、誓願の祈りは、自身の行動の出発点である。そして、仏教が促す祈りとは、この「誓願にほかならない。
仏典に説かれる勝(しょう)蔓(まん)夫人という女性は、仏の境涯を目指し、釈尊に誓いを立てる。「私は、孤独な人、不当に拘禁(こうきん)されて自由を奪われている人、病気に悩む人、災難に苦しむ人、貧困の人を見たならば、決して見捨てません。必ず、その人々を安穏(あんのん)にし、豊かにしていきます。
幸福を祈る。祈ったなら、そうなるために動く。動いたら、また祈る。
12、「新たな日常」
紀元前から、天然痘は人類を苦しめてきた。英国の医学者・ジェンナーは、この病を予防する「種痘(しゅとう)」を開発したことで知られる。だが、彼より6年早く種痘開発に成功した日本の医師がいた。緒方春朔(おがたしゅんさく)である。
その方法は、天然痘の患者のかさぶたを取り、健康な人の身体に入れ込むというもの。最初の治験で効果が認められたもの、多くの人が怖がり、敬遠した。しかし、緒方は諦めず、さまざまな場で、安全性を力説。種痘は少しずつ広がり始めた。
緒方は治療法を伝えるため、カナ交じりの文章で、分かりやすい解説書を作成した。彼の業績を知り、医学を志す入門者には、種痘を金儲けや売名に利用しないこと、貧富や貴賎(きせん)で患者を差別しないことを誓わせた。
一方のジェンナーも、自身が発見した種痘法の特許を申請しなかったという。特許を取れば、種痘が高価になり、全ての人に行き渡らないからだ。緒方もジェンナーも、その献身は“患者のため”との一点に貫かれていた。
天然痘は40年前の5月に根絶された。人間の歴史とは一面、感染症との闘いの歴史である。その長い闘いの中で積み上げられた苦労の結果が、コロナとの闘いにも生きている。
13、「不屈の人」の胸には、いつも希望の言葉が生まれている
「私は我が運命の支配者 我が魂の指揮官なのだ」。これは19世紀イギリスの詩人ヘンリーの詩の一説。題名の「インビクタス」はラテン語で「不屈」を意味する。
ヘンリーは十代で結核に感染して、カリエスになり、片足を切断。そんな自分を励ますために作った詩だ。さらに彼がモチーフとなって誕生したのが、小説『宝島』に登場する片足の海賊シルバー。友人であるスティーブンソンが創作したものという。
後年、南アフリカのマンデラ氏が人種差別と闘い、27年半もの間、牢獄にいた時、心の支えとしたのも、この詩だ。感染症との闘いから生まれた魂の継承劇として、ウィルス学者の加藤茂孝氏が自著『人類と感染症の歴史』でつづっている。
コロナ禍と闘う、医療に従事する方から「すべての患者の皆さんの生命力を引き出せるようにと毎日、真剣に挑戦しています」と声が届きます。
14、心掛け
負債の返済や闘病を経て、70歳で大学院へ。も猛勉強を重ね、77歳で博士号を取得した経営コンサルタントの吉岡憲章さんが、第二の人生を充実させる秘訣を語っている。(「潮」2020 6月号)
人は年齢を重ねると、つい過去の“手柄話”が多くなりがち。吉岡さんは友人と話す時には「昔話をやめよう」と呼びかける。自分が未来を見据えた話をすれば「同じように前向きな話ができる良い仲間ができてくる」と。
さらに、愚痴っぽい話になりそうなときにはいこう問いかけてみる。「その話、孫にどう話す?」すると皆、「おっ、これはいかん」と背筋がシャンとするという。
「心掛け一つで、どんな形でも周囲に付加価値を生む人生を送ることはできます」・・・あらゆる世代に通じる、自他共に高め合うヒントといえよう。
いたずらに不安をあおるような情報が氾濫する昨今。それに埋没すれば、かつての日常への憧憬(しょうけい)が浮かぶばかりで、心は満たされまい。